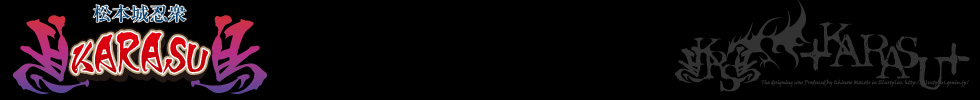松本城忍衆 烏-KARASU-
小笠原秀政松本城入封〜秀と旧・松本城忍衆との再会〜(1613年)
1613年、松本藩の藩主であった石川康長が改易されると、飯田城にいた小笠原秀政が松本城へ入封した。
かつてこの地を治めていた小笠原氏の返り咲きに、民衆も皆盛大に歓迎したという。
秀政が松本城へ入城する際、大名行列の前方を警護する一人の忍びがいた。
小笠原秀である。
大名行列から少し離れ、周囲を警戒しながら木々の合間をすり抜けていくその姿は、立派な忍びに成長したものだと秀政も喜んだ。
こうして無事に秀政は飯田城から松本城への入封を済ませ、大名行列の後方、最後の一人が入城するまでを見事に警護し遂げた秀。
その姿を旧・松本城忍衆の御頭を務めた石川玄斎をはじめ、他の元忍衆も興味津々の様子で見届けていた。
「ねぇねぇ、あれが秀?」
興味深げに訪ねたのは、旧・松本城忍衆の最年少、堀田楓である。
旧・松本城忍衆は、第二次上田合戦より更に前、まだ楓が生まれたばかりの頃に、秀政や登久姫、秀のいた下総古河を全員で訪れたことがあった。
しかし楓は赤子だったがために、彼の姿は知らなかった。
「うん、そうね。本当に忍びになったんですね。玄斎先生。」
楓の問いにそう答えたのは戸田美影。
第二次上田合戦での生き残りであり、秀とは幼い頃よりこの松本城で育った。
「うむ。秀政様から正式に忍びとしての位を賜ったらしい。全く…武士から忍びになろうなどと。」
玄斎は少し腑に落ちない様子だが、立派に成長した秀に内心嬉しい気持ちもあった。
「初動が甘いな。あれでは手練れでなくとも先が読める。」
冷静な視線でそう語ったのは水野氷冷。
美影と同じく
第二次上田合戦での生き残りであり、秀とも幼馴染みにあたる。
「かぁ〜、厳しいねぇ。途中から忍びの道に進んであの動きなら大したもんじゃねーか?なぁ楓?」
彼もまた第二次上田合戦での生き残りではあるが、元々旧・松本城忍衆ではなく、徳川の忍びとして参加していた松平樹。瀕死の重傷を負い、玄斎に助けられた忍びである。
「んーどうかなぁ?あ、ねぇ終わったんじゃない?行ってみようよ!」
そういうと楓を先頭にみんな秀の元へ駆け寄った。
「ばー!こんばんはー!楓です!えっとぉ、初めましてになるのかな?」
秀の元へ着くなりいきなり自己紹介を始める楓。
すると秀は、
「誰だお前」
当然の反応である。
「秀!久しぶり!覚えてる?」
「え、お前…美影!?おぉ美影じゃねーか!!久しぶりだな!!」
楓の後ろから駆け寄り声をかけた美影に秀はスカーフを外しながら笑顔でそう答えた。
「この子楓ちゃんだよ?覚えてない?下総のときにいたでしょ?ほら堀田さんの」
「ん?…あぁ!お前あんときのガキか!?でかくなったなぁ!…いやなってねーか(笑)」
「どもー!思い出してくれた〜?」
身長の低い楓に対して秀のとぼけた反応にも、楓は笑顔でそう答えた。
「お前の親には本当に世話になってなぁ。…って、あれ?もしかしてあれ、氷冷?」
秀は美影の後方から近付いてきた氷冷を指さした。
「そう!氷冷あんなに美人になったのに良くわかったね!」
「いや、だって目つき変わってねーじゃん(笑)」
「ちょっと秀(笑)」
「え?あれ昔からなの?そうなんだウケるー(笑)」
そうやって3人で笑い合っているとそこへ氷冷がきて、
「お前ら全部聞こえてるんだからな。」
「わりぃって(笑)元気そうだな氷冷。」
「お前もな。」
そういうと普段は無口で冷静沈着な氷冷も、久々の再会を一緒に喜び合った。
「お務めご苦労。久しぶりだな秀。」
氷冷たちの後ろから玄斎が声をかけると、3人のくノ一は軽く一礼して道を空けた。
「おう、色々世話んなったな玄斎さん。」
玄斎は秀政からの頼みで密かに飯田城へ赴き、数年前まで秀に忍術の修行をつけていたのであった。
「それにしても立派になったじゃないか。最後に会ったのは確か、登久姫様のご葬儀以来か。」
「…あぁ、そうだったっけ。」
登久姫は城主・秀政の正室で、この6年前に病によって亡くなられていた。
当時、秀にとって秀政と共に最も大切な存在であった登久姫の死は、秀の心に大きな傷を負わせた。
先ほどまでの和やかな雰囲気が一変し、誰もが少し重い空気が流れていた。
するとそこへ玄斎の陰から樹が顔を出した。
「よっ!なぁ玄斎先生。俺も紹介してくれよ。」
場の空気を顧みない屈託のない笑顔で秀と玄斎に話しかけた。
すると…
「貴様!」
突然抜刀し、樹の額へその切っ先を突き当てた。
「何者だ。その紋を外せっ!!」
樹の額には登久姫と同じ葵の紋が刻まれたハチガネが巻かれている。
「秀!!」
「あ?何だ急に?」
「おいやめんか秀!この者は、松平樹。我々の仲間だ。」
「…松平だと?」
秀は少し驚いた表情でそうつぶやいた。
この時代、松平姓を名乗れる者は将軍・徳川家と関わりの深い家柄であることを示していた。
「そうだ。徳川家より上田合戦に我々と共に参戦し、瀕死の重傷を負った樹を、私がここへ連れてきた。」
「知らんな。この敷地内で葵の御紋をつけていいのは、登久姫様だけだ。」
秀は登久姫と同じ家紋をつけた樹が気に入らなかった。
「なんだか知らねぇが、それは聞けねぇ相談だなぁ。俺だって一応、徳川の人間なんでね。」
「…貴様っ!」
秀は樹のハチガネに押し当てた切っ先を、より強く押し出した。
「いい加減にしないか秀!
自分の言っていることの矛盾に気付かぬか?
自分のことに置きかえてみろ。
お前はその小笠原の三階菱を外せと言われて簡単に外せると思うのか?」
玄斎は秀の忍び装束に刻まれた小笠原家の家紋、三階菱を指さした。
しかし秀は一向に引こうとしない。
「秀政様の命(めい)とあらば容易いこと。
この紋をつけたものに城内をうろつかれては、秀政様のお心が休まらぬ!
」
頑ななまでに刀を納めようとしない秀に、玄斎は
「馬鹿者が!!
秀政様はそのように心の狭い人間ではないわ!
秀政様がこちらへお越しになる以前に、既に樹のことはお聞き入れくださっておる。
それに秀、今お前が突き当てているその御紋は、登久姫様と同じ葵の御紋ということを忘れるな!
」
その言葉に秀はふと我に返り、樹のハチガネから切っ先を離した。
「…チッ。俺は絶対に認めないからな。任務完了の報告に行ってくる。」
秀は怒りをグッと押し殺しながら刀を納め、本丸の方へ歩き出した。
「またあとでね秀!」
「またねー!」
「…おう!たくさん話用意しとけよ!」
美影と楓の問いかけに、秀は右手を挙げて明るく応えたが、振り返ることはなかった。
「はぁ…、すまなかったな樹。
悪い奴ではないんだが…秀政様と登久姫様のことになると急に見境がなくなるものでな。
」
「まぁ良いって事よ。あいつにとってお二人はそれだけ大事な存在ってことなんだろ?」
樹はそれでも秀の行動に一定の理解を示した。
「登久姫様…私のような者にもとても優しくしてくださった。
一人この地に還られた秀政様は今、何を思ってらっしゃるのか…。」
「うん…それは秀にとっても同じ事なのかもね。」
「登久姫様かぁ、お会いしたかったなぁ。」
「楓なんて小さい頃に抱っこまでしてもらってるんだぞ?」
「えぇ!?そうだったの!!??」
「あぁ忘れもしない。あれは羨ましかったな。」
「氷冷それちょっと意外(笑)」
登久姫は凛としていながらも誰にでも優しく慈愛に満ちた姫君で、秀だけでなく誰もが慕い敬っていた。
いつの間にか自然と登久姫との思い出話に花が咲いていた。
「あのー、俺はやっぱしばらく引きこもってた方がいいんですかね?」
「はっはっは、気にするな!お前と登久姫様は似ても似つかぬからな!」
「って、そりゃそうでしょーよ!!」
こうして小笠原秀政の一行は、松本城への返り咲き果たすと共に、旧・松本城忍衆の面々も秀との再会を果たしたのであった。
※すべてフィクションです。