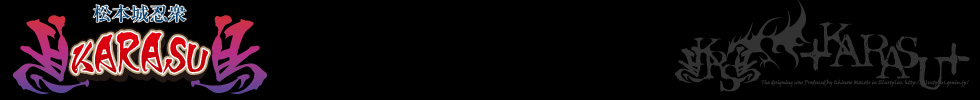松本城忍衆 烏-KARASU-
忍び襲来(1613年) 其の三
忍び装束の男は瞬時に天守最上階に到達し、今度は内部の確認もそこそこに中へと侵入した。
すぐ階下には先ほどまで戦っていた美影がいるためだ。
もたもたしていては追いつかれてしまう。
しかし突然、男の全身をこれまでに感じた事のない恐怖が包んだ。
「なんだこれは・・・」
気付けば赤い光のカーテンのようなものが部屋中を包んでいた。
部屋中を見渡していると、天井に人影があった。
「お粗末だな。」
人影はそう言って飛び降りた。
忍び装束にカラスの羽根で作られた衣をまとい、口元はチェック柄の派手なスカーフで覆われている。
天守を守る小笠原秀である。
「深志流忍法小笠原式結界術。俺を殺さない限りここから出ることは不可能だ。」
「(しまった、内部結界か…)」
内部結界とは外部からの攻撃に対し人や物を守る結界とは違い、結界内部の者が外部に影響を与えないために作り出す結界のことで、結界内部の者が自力で外に出るためには術者を説得するか殺すほか術(すべ)はない。
飯田城奇襲防衛戦の際に城壁に返り血一つ飛んでいなかったのはこの術のためである。
この術は秀がまだ忍びを目指していた頃、城に損害を与えないために最初に覚えた術でもある。
「秀っ!!」
すぐ階下にいた美影が階段を駆け上がってきた。
「よう美影。邪魔すんなよ。こいつは俺がやる。」
「気をつけて秀!伊賀の手練れよ!今すぐ結界を解いて!」
「へぇ、あんた伊賀の者か。大丈夫だって美影、そこで見てろ。勝手に解くんじゃねーぞ。」
内部結界は外部から同等の術をぶつける事により解除できるが、美影はひとまず様子を見守ることにした。
「(仕方がない…)お相手いたそう。」
男はこれまで防御のために逆手に持っていた小太刀を持ち替えた。
「行くぞ」
そう言うと秀は居合いの構えで突進した。
「(早いっ!!)」
男は小太刀の腹を左手で押さえて秀の居合いを防いだが、あまりの威力に身体が揺らいだ。
「(…なんて力だ)」
そのまま秀は納刀し、上へ跳んだ。
男も体勢を立て直すと同時に小太刀で突いたが悠々と交わされ、秀は空(くう)を蹴って左へ曲がった。
「(この者…一体)」
「…秀、え…なんで?…すごい、なんて速さなの。」
秀は凄まじい速さで空を蹴りながら斬撃を繰り返し、男は完全に防戦一方となっていた。
美影は秀が忍びになってから、秀の戦う姿を見るのはこれが初めてであり、
無論、他のメンバーもまだこの光景を目の当たりにした事はない。
結界の外にいる美影は、秀の動きを眼で追うことさえままならない状態であった。
秀は正面から堂々突進し、抜刀したが男の小太刀をかすめて振り切った。
男はその隙をついて袈裟斬りを仕掛けた。
しかしその太刀が秀を捉える前に、秀の左斬り上げが男の胴を切り裂いた。
右手で振り切った刀を背面で左手に持ち替え、そのまま斬り上げる技、侍の頃に覚えた『背陰刀(はいいんとう)』である。
「がっっ!!」
男は瞬時に身を引いて避けようとしたが間に合わず、その斬撃によって吹き飛ばされた。
秀は刀に付いた血をビュッと一振り払い、納刀しながら
「浅いか。」
と呟いた。
男は片膝をついたまま左手で胸を押さえ、肩で大きく呼吸している。
男の胸は鎖帷子を切り裂かれ、かなり出血しているようだ。
「(この動き…侍…?いや、忍びと侍の動きが融合されている…しかしこの力と速さ…桁違いだ。)」
男は戦いながらにして秀がかつて侍であったことを感じ取っていた。
「…お主、一体…」
「それはこっちの台詞だろ。ここに何の用だ?」
男はゆっくりと立ち上がり、再び小太刀を逆手に持ち替えて忍術の構えをとった。
忍術勝負なら分があるとふんだためだ。
「仕方ねぇ。」
そういうと秀も忍術の構えをとり、男より先に術を発動させた。
「深志流忍法召喚術 烈火」
秀の周りに発生した炎が一斉に男に襲いかかった。
内部結界がなければ天守が一気に焼けこげてしまうような凄まじい火力である。
男も慌てて術を繰り出した。
「伊賀流忍法 防衛の術」
すると男を囲むように青白い光りの壁が出現し、炎を一切寄せ付けない。
しかし炎の威力も衰える事はなく、容赦なく男に襲いかかる。
「(なんという火力だ…防衛術の上からでもこの熱か…)」
男は焦っていた。
その光景を目の当たりにした美影もまた、秀が召喚した炎の巨大さに驚きを隠せなかった。
「へー、防衛術か、おもしろい。どういうわけか俺は火と相性が良いみたいでな。防ぎきってみろよ。」
そういうと秀はおもむろにもう片方の手も忍術の構えをとり、両手を前方に突きだした。
「烈火 灼熱焦土!」
「…えっ!?」
男を取り囲んでいた炎が突然爆発し、更に巨大な火柱となって男を丸ごと包んだ。
「(…どうして秀が…この術を!?灼熱焦土は烈火の上位忍術…、楓ちゃんだってまだ使えないのに。)」
男の姿はもはや確認できないほど巨大な火柱が渦を巻き、男を取り囲んでいる。
「肺から焼かれる気分はどうだ?防衛術なんか何の役にもたたねーだろ?」
「コ…ココ…コォォォォ…(まずい…意識が…)」
秀の声は炎の音にかき消されて男には届かなかったが、秀の言うとおりであった。
防衛術で炎そのものは防ぎきれても、男の喉は熱によって焼かれ、呼吸もままならない状態であった。
しかしこれだけの至近距離ならば、少なからず秀にもその熱は影響を与えているはずだ。
「秀っ!!」
かすかに聞こえた美影の声をよそに、秀は刀を抜き、左肩に付けて忍術の構えをとった。
炎の勢いが衰えぬ中、秀が静かに呟いた。

「とどめだ」
するとゾクッとするようなまがまがしい殺気が漂い、炎はみるみるうちに消失していった。
忍び装束の男はうつ伏せに倒れていたが、薄れゆく意識の中、顔は秀の方を向き、身体は弱々しい防衛術でかすかに守られていた。
秀の刀から赤い霧のようなものが発生し、秀の眼が徐々に赤く光り出す。
「…何…この空気…何なの…」
美影は震える身体を必死に抑えようとしていた。
すると突然、美影の背後から
「そこまでだっ!!」
その声とほぼ同時に、突然結界が解かれた。
美影が振り返ると、そこには忍術の構えをした玄斎の姿があった。
「…玄斎先生」
その姿を秀も確認し、忍術の構えを解いて
「おい、何すんだよ玄斎さん。」
そう言ったときには、秀の眼は元に戻っており、まがまがしい空気も消えていた。
そして玄斎の背後から樹が駆け上がってきた。
「半蔵さん!!」
樹はそう叫ぶと、倒れている男に駆け寄った。
「ハンゾウ…さん…?」
樹は倒れている男を抱きかかえ、
「おい半蔵さん、大丈夫かしっかりしてくれ!」
と必死に身体を揺すっている。
「おいなんだ貴様勝手に戦場(いくさば)上がってきてんじゃねーぞコラ。 知り合いか?」
秀は水を差された怒りをあらわにしながら刀を肩に担ぎ、樹に迫っていく。
「バカヤロー!お前か!半蔵さんこんな目に合わせやがって!」
「だから誰なんだよそのハンゾウさんっつーのは!!」
すると楓を担いだ氷冷が階段を駆け上がってきた。
「…なんだこれは…?」
氷冷にはこの状況を理解することができず、
楓はまだ意識がないようだ。
一部始終を見守った美影は玄斎に問いかけた。
「玄斎先生、ハンゾウさんってまさか…?」
すると玄斎は秀と樹の間に割って入り、皆の顔を見ながら
「そうだ、この御方は徳川家にお仕えなさっている伊賀同心の支配役。服部家当主・服部半蔵殿だ。」
「えぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇっ!!!!!!!!!???????????????」
「(えぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇっ!!!!!!!!!???????????????)」
「えぇぇぇぇ…誰それ?」
つづく
※すべてフィクションです。