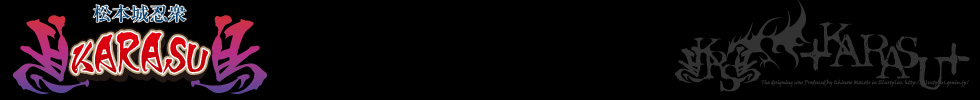松本城忍衆 烏-KARASU-
忍び襲来(1613年) 其の五
美影の分身術に対し注意を促した半蔵。
しかしそれは秀に対しても同じように注意が必要だという。
「半蔵殿、それはどういうことですか?」
皆秀と同じ疑問を抱き、玄斎が問いかけた。
「主も小笠原といったな。秀政殿とは?」
「はい、親戚関係にあたるようで、先祖は代々武士でございました。」
秀が話すよりも先に玄斎が話し始めた。
秀以上に半蔵の言葉が気になって仕方がないようだ。
「では深志流忍法小笠原式というのは、彼が?」
「いえ、深志流忍法帖の中に【小笠原式】の記述があるのです。
恐らく、過去に小笠原氏の者かがかつて此処の忍衆だったのではないかと。」
「そういうことか。あの内部結界はそこから学んだのだな?」
「ああ。城を傷めずに場内で戦うには必須だからな。」
「お前ガキか!服部家当主だぞ言葉をつつしめ!」
秀のタメ語に樹がつっかかってきたが、秀は黙れとばかりに無視している。
「よいよいこの方が話しやすい。美影はこの戦を見ていたな。どう感じた?」
「はい、私も秀が忍びになってから戦う姿を見るのは初めてで…
秀がこんな力を持っていたなんて…とても信じられませんでした。」
「なんだ?そんなに凄かったのか?」
一部始終を見守っていた美影は率直な意見を述べた。
「まさか秀が…烈火の上位忍術、灼熱焦土まで使えるようになっていたなんて。」
「なんだって!?」「何…?」「なんだと?」
美影の言葉に一同が驚いた。
すると秀は慌てて
「おいおいんなもん使えるわけねーだろ!本当に見てたのかよ、烈火だってままならねーってのに。」
と否定したが、それには美影も驚いた。
「…え?」
「…やはりそういうことか。」
半蔵は何かを感じとっていたようだ。
「記憶が曖昧になっているようだな。
そう、美影の言うとおり、【烈火 灼熱焦土】という術は確かに発動された。
それがしもその術によってあれほどの重傷を負ったのだ、間違いない。
」
「秀が…灼熱焦土を…?」
「恐らく全てはあの内部結界が理由だろう。
あの術には単に結界としての役割だけでなく、術者の能力を飛躍的に高める効果があるのではないか。」
「何だよそれ。あんたを負かせたのは俺の実力じゃねーって言うのかよ。」
「秀!!…すみません半蔵殿、しかし忍法帖にそのような記述は無かったかと…。」
「いや、間違いあるまい。
あの力、あの身のこなし、そしてあの忍術。
どれをとってもそれがしがこれまで経験した事のないほど強大であった。」
「マジかよ…半蔵さんが経験したことないってお前…」
「その反動がその記憶障害ではないのか?」
「覚えてるって。俺の斬撃に耐えきれずに忍術勝負しかけてきたんだろ。だから烈火で。」
「その後は覚えているか?」
「あと?…あぁ、おっさんに邪魔されて終いだろ。」
「…秀。」
半蔵は灼熱焦土で意識を失いかけていたためその後のことはハッキリと覚えていなかったが、美影と玄斎は明らかな“間違い”に気付いていた。
「秀、お前【三階菱】を発動させようとしただろう?だから止めたのだぞ?」
「三階菱?そんなことしてたら瞬殺だろ。」
玄斎と美影は目を丸くして驚いたが、それ以上何も言えなかった。
「そうか、恐らく灼熱焦土辺りから何かが乗り移ったように戦っていたようだな。
皆もこれでわかったであろう。少なくともあのとき戦っていたのは、秀だけの力ではない。」
玄斎達は半蔵の言葉に返す言葉がなかった。
秀も周りの反応に困惑しつつ、「・・・なんなんだよ。」と呟いた。
「皆もわかるな。このような大術には必ず相応の反動を伴う。
記憶障害だけならまだしも、術者自身を死に至らしめたり周りの者にまで影響を及ぼす術まである。
」
「それが…美影の分身術や、秀の内部結界にも可能性があると…?」
「そういうことだ。あくまでも可能性のひとつだが、一番恐ろしいのは充分な発動条件を満たさずに強行発動させてしまった場合、反動よりも大きな罰則がつくことが多い。伊賀の記述でも術者の死や寿命の添削、最悪の場合一族が滅んだ例まであるらしい。例えば秀の記憶障害が術を発動させたことによる反動だった場合、下手に発動させたときの罰則はそれを優に上回る。全ての記憶を無くしてもおかしくはないということだ。」
「マジかよ・・・。」秀を始め一同は半蔵の言葉に驚愕していた。
「・・・しかし。ではそれは、どのようにしたら防ぐことができるのですか?」
「無論、一番は危険な術は使わぬことだ。伊賀流忍法帖には危険と判明した術は削除されている。しかし大術を使わぬというわけにもいかない場合がある。そのときのために、大術は師から直接受け継いている者もいる。」
「では、私の分身術も使わぬ方が宜しいのでしょうか?」
「いや、まだ危険と判明したわけではないが、しかしそうだな。確かに使わぬに超したことはないだろう。しかしせっかく自ら開発して昇華させた偉業。城の守りにも大いに役に立つ大術ゆえ、伊賀の方でも過去に例がないか調べておくとしよう。」
「宜しいのですか半蔵殿?」 玄斎の問いに半蔵は「あぁ。」と応え、美影も思わず微笑み深々とお辞儀をした。
「じゃあ俺のは?」と秀は淡い期待を寄せて半蔵に問いかけた。
「お前の内部結界は既に記憶障害という反動も判明しておる。ならば使わぬ方が良いだろう。などと言っても聞かんだろうがな。」
秀の期待はかなわなかったが、半蔵は秀の性格まで見越していた。
「秀が無茶な使い方をせぬよう、私がしっかりと見張っておきます。」
と玄斎が頭を下げると、「私も見張っています」「私も」「じゃあ俺も」と皆続いた。
「ちっ…、城を傷めずに戦うには必須だってのに。」
「まぁ使うなと言っているわけではない。極力使わん方が良いということだ。仮に使用するときはやむを得ない場合だけに限定することだな。」
秀は少し考えた末に、「わかった、“極力”、だな」と言ったが、一同は“きっとわかってない”と感じ取った。
その直後、背後から「んん・・・?」と声がして一同が振り返ると、楓が目を覚ました。
「おっ楓、起きたか?」
楓は上半身を起こすものの状況が理解できず、頭はまだぼーっとしているようだ。
「ようやく目を覚ましたか。玄斎と楓はここに残り、他の者は外してくれるか。」
4人は一礼し、階下へと下った。
つづく
※すべてフィクションです。