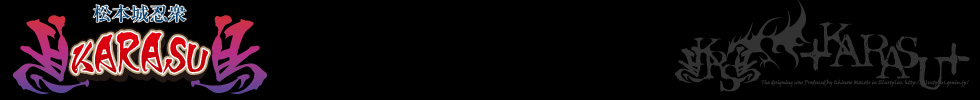松本城忍衆 烏-KARASU-
忍び襲来(1613年) 其の六
半蔵から席を外すように促された4人は、3階まで降りて話し合いをしていた。
「まさか忍術にそんな規制があったとはな…」
「まぁ規制っつーか制約だな。大術に危険性を伴うのは伊賀じゃ常識だったが、そういうもんは忍法帖にも載ってねーし、何か特別なことをしないと会得できねーと思ってたんだが。まさかお前らがねぇ…」
「本当に…、術者だけならまだしも周りに影響があるかもしれないなんて…。」
「まぁ大丈夫だって!逆に俺らにも影響出るくらいの方がお前らの負担も軽くなるんじゃないか?」
「本当にそう思うか?殿や城にも影響が出るかもしれないということだぞ。」
「殿!?…そうか、秀政様にも。」
城を守るのに適した秀と美影の大術。しかしそれは主や城をも危険に晒す可能性があるものだと知り、二人は困惑していた。
「まぁでもさ氷冷、半蔵さんも調べてくれるっつーし、とりあえずは影響なかったんだからそれまで注意して使ってりゃ大丈夫じゃないか?」
「美影の方はな。しかし罰則の事例にあった“寿命の添削”というのが気にかかる。
即死や記憶障害と違って確かめようがない。」
「そうね、でも私は大丈夫。今まで反動と思える影響は出たことがないし、仮に自分の寿命が削られていたとしても、それで殿やお城を守れるなら…それよりも周りへの影響が心配。」
「あぁ、だが最悪なのはその寿命の添削ってやつが俺ら術者じゃなくて秀政様や城に影響していた場合だな。」
「まぁそんなこと考え出したらきりがねぇよ。どうせ術を使うときなんて殿や城に危険が迫っているときなんだから。
それよりも術を出し惜しみして殿や城を危険に晒すようなことだけは避けた方が良いだろ?」
「確かにな。別段異常がないようならこれまで通り、任務遂行を最優先とすべきか。」
秀と美影は顔を見合わせ 「だな。」 「うん。」 と納得した。
「それにしても楓のやつ大丈夫かね?氷冷、あいつなんかやらかしたのか?」
「そういうわけではないと思うが、半蔵様には何か感じ取れたのだろう。」
「そういや惨敗したのは楓だけか?」
「お前は勝ったとでも思ってるのか秀?」
楓をバカにしたような言い方にイラッとした表情で氷冷が応え、秀も「あ?」っとにらみ返した。
「半蔵様、一度も攻撃してこなかったもんね。」
「ん?そうだったか?」
「私のときもだ。私達の力量を図るのが目的だったんだからな。」
「ったりめーだよ!半蔵さんが本気出したらお前らなんかもうギッタンギッタンのバッキンバッキンに…」
とまで言いかけたとき、氷冷が「あ、そうだ。」と言い階下へかけだした。
「ん?どうした?」と氷冷の姿が見えなくなったとき、半蔵、玄斎、楓が上の階から降りてきた。
楓は玄斎の陰に隠れ、どうも元気がなさげである。迎えた三人は軽く会釈をした。
「皆集まっておるか?ん?氷冷はどうした?」
「あ、先ほど急に慌てて下に行きましたが、すぐ戻るのではないかと。」
「そうか。半蔵殿はこれにてお帰りになられる。何か聞いておきたいことがあれば今のうちに聞いておくように。」
「半蔵さん、もうお帰りで?」
樹がそう問いかけると半蔵は突然あらたまり、おもむろに片膝をついて深々と頭を下げた。
「よくぞご無事でおられました。ご立派になられましたな、樹殿。」
「おいおい急によしてくれよ半蔵さん。さっきまで普通に話してたじゃないすか。」
突然の出来事に、秀と美影は顔を見合わせポカンとした顔をしている。
「え?何々?どういうこと?」
「私も聞いたときは驚いたのだがな、樹は徳川家の正当な血縁関係で、将軍秀忠様は樹の叔父にあたるそうだ。」
「えっ!?」 「・・・お前、マジか。」
樹は「半蔵さん、ばらしちゃったのかよ。」と言いながらもちょっと照れた様子である。
「樹殿は幼少の頃よりそれがしが預かり、徳川家直下の隠密となるため伊賀の忍法を学ばせておりました。」
「そう、だから半蔵さんは俺のお師匠様なんだよ。」
「今回、半蔵殿にお越しいただいたのは、樹、お前を半蔵殿の元へお返しするためでもあるのだ。」
「…え?」
玄斎の突然の申し出に、樹はとまどった。
「なんだお前帰るのか?」
美影も不安そうな顔で樹を見つめている。
「ちょ、ちょっと待ってくれよ。帰るって…今更俺が、徳川に?」
「不満か?」
「いや、不満とかじゃなくてさ。俺なんかもう…死んだことになってんだろ?」
樹の問いかけに玄斎は応えなかった。
「なぁ待ってくれよ…!俺はあのとき死んだんだ!それを玄斎さん!あんたが助けてくれた!!だから俺は誓ったんだよ。あんたに一生ついてくって!!半蔵さんには申し訳ないが…俺は帰るつもりはない!!」
「・・・樹。」
精一杯の決意だった。
「半蔵さん、申し訳ない。半蔵さんには感謝しています。でも、俺はあのとき…死にました。」
樹の目にはうっすらと涙が浮かんでいた。
それを聞いた半蔵は、「樹殿なら、そう言うだろうと思っておりました。」といい、優しい笑みを浮かべながら頭を深々と下げた。
「ご無事だっただけでも何よりです。このことは、それがしの胸の内にしまっておきましょう。」
「ありがとう…ありがとう半蔵さん。」
樹は涙をこらえきれず泣き崩れた。
玄斎が「本当によいのだな樹。」と問うと、樹は何度もうなずいた。
「帰んねぇのかよ。」と冷めた表情で見つめる秀とは対照的に、美影は安堵と同時にもらい泣きをしていた。
そこへ氷冷が階段を駆け上がってきた。
「あ、半蔵様。 ん?なんだこの状況は…」
秀が半蔵と戦ったあとと同じように、氷冷はまた状況を飲み込めずにいた。
「あ、氷冷。今ね、樹さんが…」
と言いかけたとき、手に持っているものに玄斎が気付いた。
「ん?なんだその道具は?」
氷冷は書道道具一式と真新しい掛け軸を持っていた。すると氷冷の肌はみるみる赤くなり、
「半蔵様。こ、こちらにその、書を一筆お願い致したく…。」
それはとても恥ずかしそうなか細い声だった。今で言うところのサインのお願いである。
「ちょっと氷冷(笑)」 「お前なぁ。」 「はははははっ!」
先ほどまで感動に包まれていた室内に、笑いが込みあげた。
「全くお前という奴は。」
玄斎も呆れたように笑い、半蔵は「お安いご用だ。」と快く受け入れてくれた。
こうして服部半蔵は見事松本城忍衆 烏-KARASU-の力量を図り終え、無事帰還するのであった。
※すべてフィクションです。